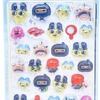こうして、ぼのぼののお遊びで始まった「見ること」という主題は、スナドリネコとヒグマの大将の確執とも呼応しあって、クライマックスを構成することになる。
“大きな生き物”ことジャコウウシは、なんだったのか。キャラクター化された森の動物たちと異なり、ジャコウウシはより動物らしく描かれており、言葉も発しない。歩む音の効果音だけが、言葉の代わりに響いてくる。要するにジャコウウシは、森の動物たちの構成するーーヒグマの大将が守ろうとしているーー社会の外側からやってきた存在なのだ。それを「運命」と呼んでもいいだろうし「世界の摂理」と呼んでもいいだろう。いずれにせよ「社会」の中にいる限り、「見ること」しかできない、特別な存在なのである。
このように「見ること」をめぐる主題は着地するが、では「どうして楽しいことは終わってしまうのか」という疑問はどのように取り扱われるのか。
ジャコウウシが歩み去り、家路につくぼのぼの。そこでぼのぼのは、スナドリネコに「どうして楽しいことは終わってしまうのか」と尋ねる。スナドリネコはそれに対し「悲しいことも終わるため」と応える。
スナドリネコは続ける。「楽しいことも、悲しいこともみんな終わる。それは生き物が、何かをするために生まれてきたわけではないからだろう」
では、生き物はなぜ生まれてきたのか。「見るためかもしれない」
スナドリネコはこんなふうに説明する。生き物は「見られるものを見るため」に生まれてきた。でも見ているだけで退屈になったら「終わってしまうこと」をやってみればいい。必ず終わってしまうことは、そのときのためにあるんだ、と。
このラストの会話は絵コンテの初稿には存在せず、改定時に付け加えられたものだ。しかも改訂版もAパターンとBパターンの2種類が描かれ、最終的にBパターンが採用された。おそらくマンガであればここまで踏み込んだ会話が登場することはなかったのではないか。映画というメディアが、2時間のまとまりーーつまり終わってしまうことーーを要請した結果、台詞という形で「見ること」と「楽しいことが終わってしまうこと」をしっかりと結びつけるシーンが作られることになった。ここには三題噺のサゲにも似た、無関係なものが実は底流でつながっていたことが明らかになるカタルシスがある。
映画は冒頭のカットとは逆に、カメラが大きく引いていくことで締めくくられる。映画は朝から始まり、ラストは夕景である。夕日に包まれた森の全景を見るとき、観客はそれが単なるぼのぼのたちの森というだけでなく、「世界」を見ているような感覚になるはずだ。
観客はこのラストシーンに到達したことで、「見ることだけしかできない」という世界に対する姿勢と、映画に対する自分たちの関係が相似形にあり、映画を見ることが「見ているしかないこと」へのレッスンであることを知る。また同時に「映画は終わってしまうもの」で、それが世界に対して何もできない人間が、この世に飽きないための営みであることも思い出すのだ。
なお「見ること」と世界の関係について、いがらしみきおは『I【アイ】』という2010年からの連載作作品でさらに突き詰めて描いている。また2016年に出版された『ぼのぼの』41巻では、ぼのぼのの母がどんな人物だったかが初めて明かされ、そこでは「悲しみ」を軸にした物語が展開される。それは「楽しいことはなぜ終わってしまうのか」という本作の問いかけが反転した形の物語でもある。『I【アイ】』も『ぼのぼの』41巻もともに東日本大震災(宮城県在住のいがらし自身も被災者となったという)が起きたことを受けて描かれた作品である。しかしこうして振り返ってみると、映画『ぼのぼの』の中に、この2作につながる原型はすでに宿っており、それゆえに映画『ぼのぼの』は、公開から四半世紀を超えた今でも普遍性をもった作品として観客に迫ってくるのである。
【藤津 亮太(ふじつ・りょうた)】
1968年生まれ。静岡県出身。アニメ評論家。主な著書に『「アニメ評論家」宣言』、『チャンネルはいつもアニメ ゼロ年代アニメ時評』、『声優語 ~アニメに命を吹き込むプロフェッショナル~ 』、『プロフェッショナル13人が語る わたしの声優道』がある。最新著書は『ぼくらがアニメを見る理由 2010年代アニメ時評』。各種カルチャーセンターでアニメの講座を担当するほか、毎月第一金曜に「アニメの門チャンネル」で生配信を行っている。